今回は、食中毒の種類と特徴について紹介します◎
主な細菌性食中毒とウイルス
まず初めに、注意が必要な細菌性食中毒とウイルスを紹介します◎

特徴に加えて予防対策も紹介するので、心掛けるピヨ!
細菌性食中毒菌(感染型)
サルモネラ菌
【原因食品】肉・鶏肉など
▶︎鶏卵は近年、汚染率が増加している。
また、殻だけでなく、中身も汚染されていることもあります。
【特徴】
- 自然界に広く分布する。
- 家畜、ニワトリ、ペットなどの腸管に存在する。
- 菌は熱に弱い
- 自家製マヨネーズやオムレツ、手作りケーキなどから感染することがある。
【症状】発熱、へそ周辺の腹痛、下痢、嘔吐など。水様便や血便がでることもある。
【潜伏期間】8〜48時間
【予防方法】
- ネズミ、ゴキブリなどの害虫を駆除する
- 十分に加熱する
- 食肉類や鶏卵を生で食べない
腸炎ビブリオ
【原因食品】生鮮魚介類・その加工品など。
まな板や包丁などから二次汚染した弁当が原因になることもある。
【特徴】
- 海水(塩分)を好み、塩分3〜5%で増殖する。
- 増殖速度は速いが、真水や加熱に対する抵抗力が弱い。
【症状】激しい上腹部の痛み、下痢、発熱、嘔吐など。
【潜伏期間】10〜18時間
【予防方法】
- 手洗い、まな板・包丁など調理器具や布巾を熱湯消毒するなど、洗浄を徹底する。
- 食材を真水でよく洗う。
- 十分に加熱調理をする。

カンピロバクター
【原因食品】肉料理・飲料水。
特に鶏肉の加熱不足が原因となる。また、サラダや生水なども原因となることがある。
【特徴】
- 鶏・豚・牛などの腸管に存在する。
- 微好気性で、酸素濃度が5〜15%で増殖する。
- 常温の空気中では徐々に死滅する。
- 熱や乾燥に弱い。
- 潜伏期間が長い。
- 少量の菌で発症する。
【症状】腹痛、下痢、血便、頭痛など。発熱することも多く、倦怠感や筋肉痛、悪寒を伴うことから、風邪の初期症状と間違えやすい。
【潜伏期間】48〜168時間(2〜7日)
【予防方法】
- 十分に加熱調理する。
- 井戸水は塩素消毒、または煮殺菌をする。
細菌性食中毒菌(食品内毒素型)
黄色ブドウ球菌(毒素:エンテロトキシン)
【原因食品】食品全般
【特徴】
- 人の鼻、のどの粘膜、毛髪、傷口、あかぎれ、動物の皮膚やほこりなどに存在する。
- 切り傷やニキビなどを化膿させるため、化膿菌とも呼ばれる。
- 菌自体は熱に弱いが、増殖する時に生産される毒素は熱に強い。
- 加熱殺菌しても、残った毒素が食中毒を引き起こすことがある。
【症状】激しい嘔吐、下痢、腹痛など。
【潜伏期間】1〜3時間
【予防方法】
- 手指や腕に傷口やあかぎれがある時は、調理の際、使い捨て手袋などを使い、直接食材に触れないようにする。
- 手指の洗浄、消毒を徹底する。
セレウス菌:嘔吐(毒素:セレウリド)
【原因食品】米飯・麺類
チャーハン、ピラフ、オムライス、スパゲッティ など
【特徴】
- 土壌、水中、ほこりなどに芽胞として存在する。
- 農作物などを汚染する。
- 日本で多発。
【症状】嘔吐、腹痛。
【潜伏期間】1〜5時間
【予防方法】
- 調理後の食品は室温に放置しない(特に、残りご飯に注意)
- 再加熱は十分に行う(中心まで熱が通るように加熱する。)
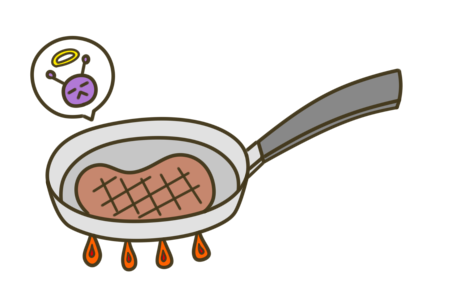
ボツリヌス菌(毒素:A型〜G型)
【原因食品】嫌気性食品
肉類のびん詰め、缶詰、真空パックなどの食品、いずし、ソーセージやハムなど
【特徴】
- 土壌や河川、海岸などに広く存在する。
- 菌自体は熱に強いが、産生される毒素は易熱性(熱に弱い)の神経毒である。
- 毒性が非常に強い。
- 酸素があるところでは繁殖しない。
- 食品内毒素型の中では、潜伏期間が比較的長い。
【症状】
- 頭痛や手足の痛みとともに、嘔吐、下痢が起きる
- 視覚・言語・呼吸障害など。重症になると、生命に関わることも。
【潜伏期間】12〜36時間
【予防方法】十分に加熱調理する。
細菌性食中毒菌(生体内毒素型)
腸管出血性大腸菌(毒素:ベロ毒素)
【原因食品】飲料水・肉類
保存や調理過程で、他の食材を汚染することがある。
【特徴】
- 赤痢の症状と見分けがつかない。
- 病原性大腸菌の一種で、毒性のたんぱく質であるベロ毒素を産生する。
- 感染力が非常に強く、集団食中毒を起こしやすい。
- 加熱調理で死滅。
- 真水や熱に弱く、消毒薬によって死滅する。
【症状】下痢、腹痛、風邪と似た症状から血便、激しい腹痛に変化する。
症状が悪化すると、意識障害や尿毒症を引き起こし、短期間で生命に関わる事もある。
【潜伏期間】24〜216時間(1〜9日)
【予防方法】
- 十分に加熱する
- 調理器具を乾燥させ、清潔にしておく
- 井戸水を含め、汚染のおそれがある水の使用は十分注意し、定期的に水質検査をする。
セレウス菌:下痢型(毒素:エンテロトキシン)
【原因食品】肉製品・プリン・スープ・ソース
【特徴】
- 土壌・水中・ほこりなどに芽胞として存在する。
- 農作物などを汚染する。
- 欧米で集団発生したケースもある。
【症状】腹痛、下痢
【潜伏期間】8〜16時間
【予防方法】
- 調理後の食品は室温に放置しない。
- 再加熱は十分に行う。
ウエルシュ菌(毒素:エンテロトキシン)
【原因食品】牛・豚・鶏・魚の保菌率が高い。
カレー、シチュー、スープ、グラタン。
食べる前日に大量に加熱調理され、大きな容器のまま室温で保存されることが原因となる。
【特徴】
- 人や動物の腸管、土壌、水中などに存在する。
- 酸素を必要としない嫌気性芽胞菌。
- 加熱調理しても生き残る芽胞を形成する。
- 学校などの集団給食を提供する施設で発生することが多いが、家庭でも発生している。
- 腸内で増殖して毒素を産生する。
【症状】
- 腹痛、下痢(嘔吐や発熱は少ない)
- 症状としては比較的軽微
【潜伏期間】8〜20時間
【予防方法】
- 前日調理で室温保存は避け、加熱調理したものはなるべく早く食べる。
- やむを得ないときは、小分けにして急速に冷却し、低温保存する。
- 食事に出す前に十分に再加熱する。
ウイルス
ノロウイルス
【原因食品】生牡蠣・ホタテ・アサリなどの二枚貝、加熱不可のもの。
▶︎ノロウイルスはウイルス粒子を含む排泄物が下水を通して海水を汚染し、二枚貝に蓄積すると考えられている。
【特徴】
- 人の腸管でのみ増殖するウイルス。
- 冬季に多発する(特に12月〜1月)が、年間を通じての発生も確認されている。
【症状】腹痛、下痢、発熱、吐き気、嘔吐、頭痛など(風の症状と似ている)
【潜伏期間】24〜48時間(1〜2日)
【予防方法】
- 十分に加熱する。目安は85〜90℃で90秒以上。
- 人から人への感染を予防する。
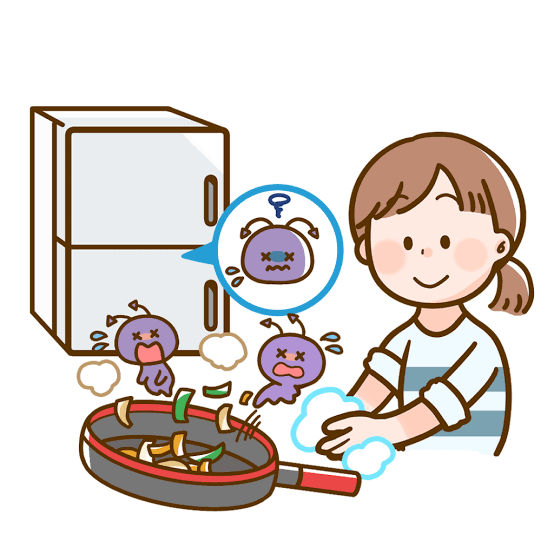

細菌細菌食中毒やウイルスによる食中毒と、沢山の種類があるピヨね!
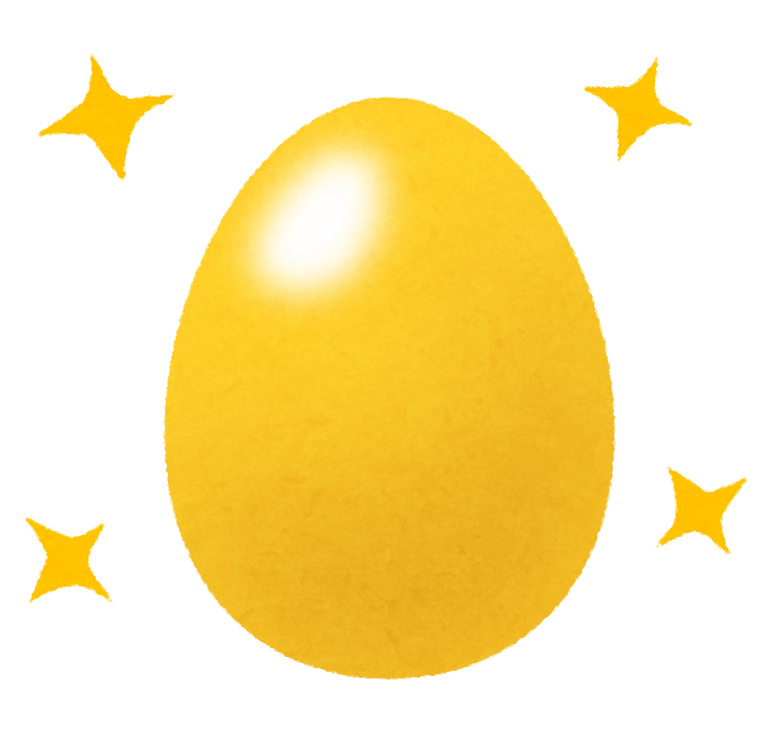
その通りです!
ひとつひとう、特徴や症状などの特徴を把握して、早めの対策を取ることが大切です◎
1番大切なことは、食中毒の細菌を発生させない事前対策ですね◎
今回は、食中毒の種類と特徴についての紹介でした◎
その他にも、【食中毒の原因】【食中毒の予防】について紹介している記事も、ご一緒に閲覧ください☆



コメント