今回は、食品の変化と加工・保存について紹介していきます☆
食品の変化と加工・保存
食品の変質
食品を長時間放置することで鮮度が失われ、外観や内容に生じる変化を変質といいます。
乾燥や変色、変形の他、異臭や有毒な物質を生じるようになり食用に適さなくなることもあります。
変質には、腐敗・変敗・発酵などがあります。

腐敗
腐敗とは、食品中のたんぱく質が、微生物(腐敗細菌)などの酵素作用により分解されて、食用に適さなくなることです。

つまり『腐った状態』のことで、悪臭がしたり、刺激の強い味になったりすることピヨね!
悪臭の原因となるのは、微生物により、たんぱく質が分解されて生じるアミン類や合硫化合物などが原因です。
保存状態が悪かった肉類や魚介類、賞味期限を大幅に過ぎた肉類や魚介類などに見られます。
変敗
変敗とは、油脂などが劣化して食用に適さなくなることです。異臭がする、粘り気が出る、色や味が悪くなるといった変化が起こります。
変敗には、食品中に増殖した微生物による酵素の働きで、糖質や脂質が分解されるものや、酸化型変敗(酸敗・酸化ともいいます。)といって、空気中の酸素や太陽光線の作用などによって起こるものがあります。
特に、油脂の酸化は、光、酸素、金属、放射線によって促進されます。
過酸化脂質という、下痢や腹痛の原因となる有害物質が生成されます。
また、油を長時間加熱したり、加熱し過ぎだりすると、アクロレインといった毒性物質が発生します。

酸敗を防止するためには、調理中に油の温度が過度に上がることを避け、使用後の油は必ず、こしてから密閉容器に入れ、暗所で保存するようにするピヨ!
発酵
食品に含まれる有機化合物が、微生物の作用によって分解され、他の化合物にる現象のうち、その作用が人間にとって有益となる場合を発酵といいます。
また発酵と腐敗は、微生物が食品を変化させるという点では同じですが、発酵はその働きを、人に有益になるようにコントロールでき、腐敗はコントロールできないため有害になります。
なお、発酵の過程で温度、湿度、時間などの条件によって食品のうま味や風味を増加させることを熟成といいます。

発酵には、キムチ・味噌・醤油・酢・塩麹・納豆・チーズ・ヨーグルト・納豆・清酒・鰹節・紅茶などがあるピヨ

発酵食品がカラダに与える、脅威的な効果を紹介している【こちらの記事】もご一緒に閲覧ください◎
食品の変質の原因
食品が変質する3つの原因
【化学作用】…食品に含まれる酸素と、大気に含まれる酸素が関わる変質。
(例)油脂の酸化による肉類や魚類などの変質や高温になることで、化学作用が促進されることもある。
【物理作用】…光線や水分、温度などが関わる変質。
(例)光線による食品の変化や酸化、水分による変色やカビの発生など。
【微生物の繁殖】…微生物による食品の変質。有害な変質として、たんぱく質性食品の腐敗があり、有益な変質として発酵がある。
(例)発酵により炭水化物は、食用アルコールや有機酸(乳酸、酢酸)を生成し、カラダに有益な働きをする。
有益微生物の種類
食品の製造、加工、保存の面で有益に働く微生物は、一般的にカビ・酵母・細菌の3つに分類されます。
〜有益微生物の種類〜
【カビ】
- 菌糸と呼ばれる細長い細胞からできている
- 自然界に広く生息し、胞子は空中に浮遊している。
- 食品に付着すると、適度な温度・湿度・栄養分・空気という条件がそろうことで繁殖し、食品を変質させる。
(例)麹カビ属・青カビ属・毛カビ属
【酵母】
窒素物や無機物を含んだ微酸性の糖液の中で、25〜30℃のときにもっとも発育する。
(例)アルコール酵母(ビール酵母・ブドウ酒酵母など)パン酵母

【細菌】
酸素がなければ生育しないもの、酸素があると生育しないもの、酸素の有無に関わらず生育するものがあります。
(例)納豆菌・酢酸菌・乳酸菌
発酵による食品加工
発酵による食品加工の例
【カビによるもの】
- 青カビ … チーズ
- 麹カビ … 鰹節
【酵母によるもの】
- ビール酵母 … ビール
- ブドウ酒酵母 … ワイン
- 酵母 … 果実酒
- 酵母 … 蒸留酒
- パンの酵母 … パン
【カビと酵母によるもの】
- 麹カビ・清酒酵母 … 清酒
- 麹カビ・焼酎酵母 … 焼酎
【細菌によるもの】
- 納豆菌 … 納豆
- 乳酸菌 … ヨーグルト・チーズ
- 酢酸菌 … 食酢
【細菌と酵母によるもの】
- 乳酸菌・酵母 … 漬物
【カビ・酵母・細菌によるもの】
- 麹カビ・醤油酵母・各種細菌 … 醤油
- 麹カビ・酵母・細菌 … 味噌・みりん
食品の変質防止と保存の方法
食品を保存するには、変質をいかにして抑えるか、つまり、新鮮さや品質を保ち劣化させないかということがポイントになります。
食品の保存方法について紹介します◎
低温法
低音では有害微生物の活動が鈍くなることを利用して、温度を下げて保存する方法を低温法といいます。
➖15℃以下で急速に冷やすことで、微生物の活動を停止させる方法を冷凍といいます。
低温法を利用したものには、冷凍食品・チルド食品があります。
【保存方法】
☆冷凍食品…日本冷凍食品協会では➖18℃以下、食品衛生法では➖15℃以下とされている。
☆チルド食品…食品の凍結点(食品に含まれる水分が固まり始める温度)である➖5〜➖3℃と、有害微生物の発育を阻止する限界温度の3〜5℃の間。
乾燥法
微生物の活動に必要な水分を取り除き、微生物の活動を抑えて保存する方法を乾燥法といいます。ただし、全ての水分を食品から取り除くのではありません。
(例)スルメ・干物など
塩蔵法
塩よ脱水作用によって、食品を脱水し、腐敗細菌の発育を抑えて保存する方法を塩蔵法といいます。
食塩水に漬ける立て塩や、食品に直接塩をふりかけるまき塩(撒塩法)といった塩漬けの方法があります。この他、砂糖漬け、酢漬け、粕漬け、味噌漬けなど、濃厚液によって微生物の繁殖を防ぐ保存方法を総称して漬物法ともいいます。
(例)新巻鮭・塩辛 など
加熱法
食品を加熱して微生物を死滅させ、酵素を不活性化して食品の変質を防ぐ保存方法を加熱法といいます。
例えば、牛乳の殺菌処理には、加熱温度と時間によって、次の方法があります◎
〜牛乳の殺菌方法〜
【超高温短時間殺菌】
▶︎120〜150℃で、1〜4秒の加熱時間
▷一般に販売されている牛乳は、超高温短時間殺菌によるもの。ロングライフ(LL)牛乳は、超高温短時間殺菌し、無菌の状態で充填されたもので、室温で約3ヶ月保存可能。
【高温短時間殺菌】
▶︎72〜85℃で、2〜15秒以上の加熱時間
▷超高温短時間殺菌に比べて低音であるため『低温殺菌』と表示されるのともある。
【低温長時間殺菌】
▶︎63〜65℃で30分の加熱時間
▷パスチャライズと呼ばれ、熱処理による成分の変性が少なく、期限表示には消費期限が用いられる。

紫外線照射法・放射線照射法
紫外線には殺菌効果があるので、食品を天日に干したり、紫外線殺菌灯を照射することで殺菌することができます。これを紫外線照射法といいます。
ただし、効果は表面だけで持続しません。
なお、放射線照射法は、日本では、ジャガイモの発芽防止の目的のみに認められている方法です。
その他
その他にも、燻煙法・空気遮断法・食品添加物による方法・長期保存食品などによる、食品の変質防止と保存の方法があります。

沢山の変質を防止する、保存方法があるピヨね〜
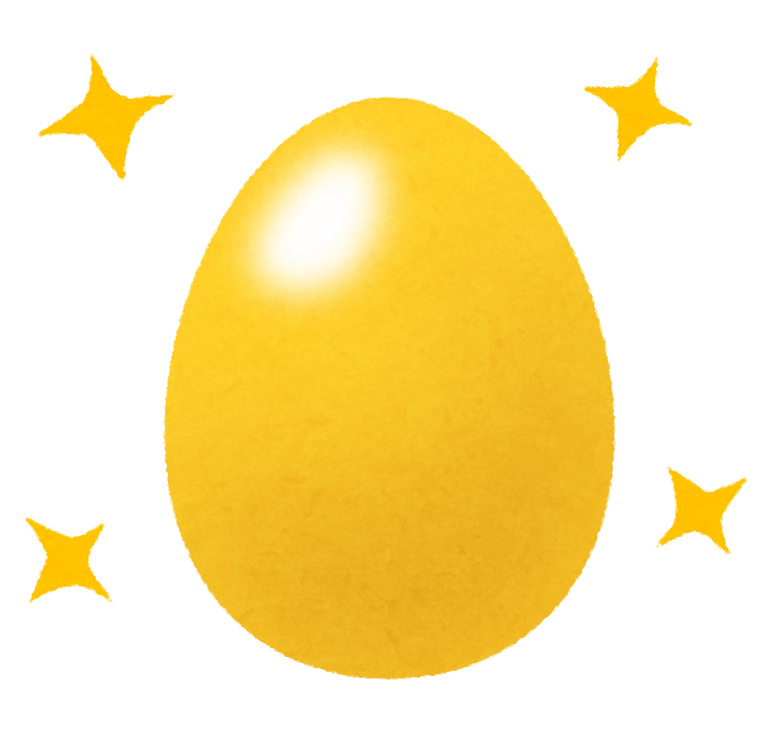
食品ひとつひとつを大切にするためにも、色んな保存方法を知っていたら、役に立ちつかもしれないですね〜◎
以上、今回は食品の変化と加工・保存についての紹介でした☆


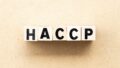
コメント