本日は、ミネラルが持つ効果・効能。そして、症状から読み解く必要なミネラルを紹介していきます☆
ミネラルが持つ効果・効能〜症状から読み解く必要なミネラル〜
私たちのカラダは体重の約95%が4大元素(炭素(C)・水素(H)・窒素(N)・酸素(O))で構成されています。
そして、残りの5%がミネラルです。
ミネラルは体内で合成できないため、食べ物から直接摂らなければなりません。
ミネラルの特徴
ミネラルはビタミンと同様に、カラダの調子を整える働きがありますが、ビタミンと異なるのは、無機質であるという点と、カラダの構成成分になるという点です。
不足すると、欠乏症を引き起こし、逆に、大量に摂取しすぎると過剰症になるおそれもあります。
ミネラルの主な2つの働き
①カラダの構成成分になる
- カルシウムやリン、マグネシウムなどは、骨や歯の構成成分になる。
- 鉄や亜鉛などは、血液、筋肉、神経、臓器の構成成分になる。
②カラダの調子を整える
- ナトリウム、塩素、カリウム、カルシウム、マグネシウムなどは、液体中にイオンとして存在し、血液や液中のph(水素イオン濃度指数のこと)や浸透圧を正常に保って筋肉や神経に刺激を与え、生体機能を調整する。
- マグネシウム、鉄、銅、亜鉛などは、エネルギーをつくる酵素や体内の新陳代謝の働きを促進する酵素の成分となったり、酵素反応を助ける。
ミネラルの種類
ミネラルは全部で約40種類あります。
その中でも、カルシウム・リン・イオウ・カリウム・ナトリウム・マグネシウム・塩素の7種類は主要無機質に、
鉄、亜鉛、マンガン、ヨウ素など、量が少ないミネラルは微量無機質に分類されます。
日本人に特に不足しがちなミネラルは、カルシウム・鉄で、鉄の摂取基準は、月経や妊娠などで鉄が失われやすい女性の方が高く設定されています。
また、ミネラルは多くの食品に含まれていますが、食品の加工や精製によって失われやすいという性質があります。
加工食品に頼りがちになると、ミネラルのバランスを崩しやすいので、過不足なく摂るよう気をつけなければなりません。

日常の食生活で、不足しがちなミネラルはカルシウム・鉄だけど、逆に過剰摂取になりがちなミネラルが、食塩に含まれるナトリウムや、食品添加物に使われるリンだピヨ◎
ミネラルの種類と主な働き・症状
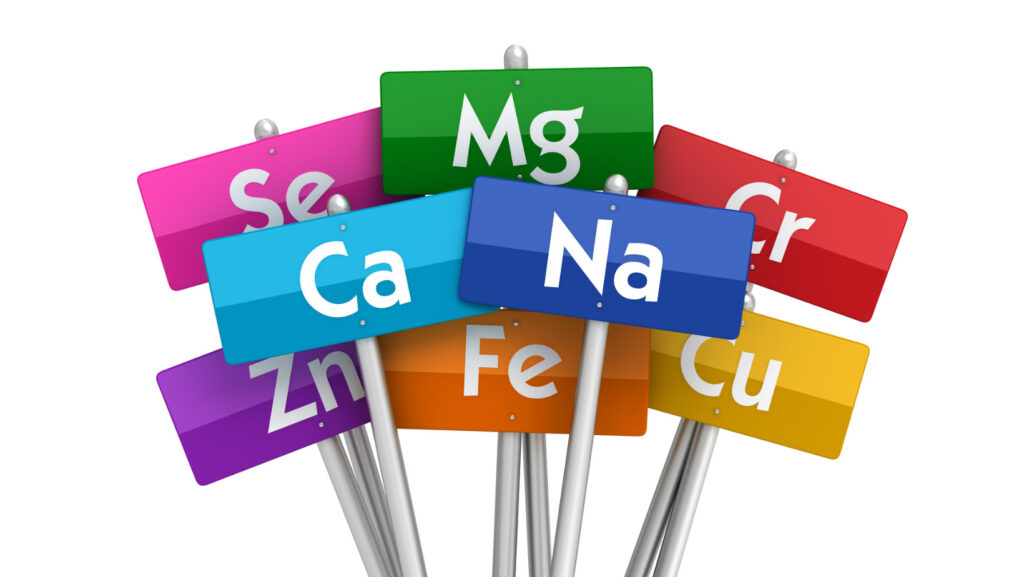
主要無機質
カルシウム(Ca)
ごく一部は、カルシウムイオンとして血液や筋肉、神経内にあり、血液の凝固を促して出血の予防・心筋の収縮作用を増し、筋肉の興奮性を抑える働きがあります。
【主な働き:骨や歯の形成/精神の安定/血液の擬古】
カルシウム濃度が低い状態が続くと、皮膚は乾燥し、角質が剥がれ落ち、爪はもろく、毛髪は粗くなります。
背中や脚の筋肉に、強い痛みを伴う痙攣がよくみられます。 やがて、脳に影響が及び、錯乱、記憶障害や幻覚といった精神症状や神経学的症状が現れます。
【主な欠乏症:不整脈/骨粗しょう症/神経過敏/イライラ/筋肉の痙攣・つり】
【多く含まれる食品:小魚/牛乳/乳製品/青菜類/海藻 など】
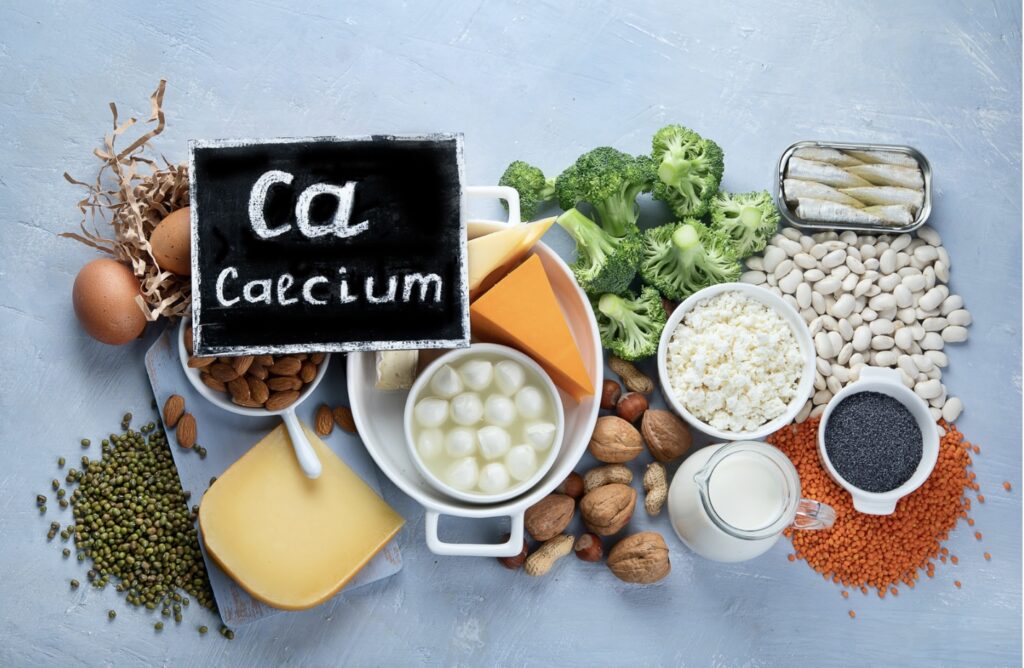
リン(P)
骨や歯を丈夫にしたり、細胞やDNAを構成したりします。そのほか、代謝のサポートや体内の浸透圧の維持などの役割も担っています。
【主な働き:骨や歯の形成/エネルギーの蓄積/細胞膜の形成】
不足すると、骨・歯やDNAの発達に支障が出やすくなります。
反対に体内のリンが過剰になると、カルシウムの吸収を妨げるなどの悪影響が出ます。
【主な欠乏症:歯槽膿漏/骨が弱くなる/筋肉の動きが悪くなる】
【多く含まれる食品:乳製品/ワカサギ/煮干/加工食品 など】
イオウ(S)
角質を軟化させる作用のほか、殺菌、殺虫作用があります。 軟膏や液剤に製剤して、ざ瘡(にきび)、疥癬(かいせん)、白癬(水虫)などの治療も用いられています。
【主な働き:皮膚・爪・髪の形成/カラダの組織を構成するアミノ酸の合成】
ニキビ、水虫などの皮膚炎、吹き出物が出やすくなり、爪がもろくなり、脱毛などが起こります。 他にも、関節の病気、動脈硬化などにもかかりやすくなります。
【主な欠乏症:皮膚炎/爪がもろくなる】
【多く含まれる食品:チーズ/卵 など】
カリウム(K)
細胞内液の浸透圧を調節して一定に保つ働きがあります。
神経の興奮性や筋肉の収縮に関わっており、体液のpHバランスを保つ役割も果たしています。
ナトリウムを身体の外に出しやすくする作用があるため、塩分の摂り過ぎを調節するのにも役立ちます。
【主な働き:血圧を正常に保つ/腎臓の老廃物の排出/筋肉の動きを良くする】
不足すると、悪心、嘔吐などの胃腸症状、しびれ感、知覚過敏、筋肉・神経症状の脱力感、不整脈などが主な症状として現れます。
【主な欠乏症:血圧の上昇/不整脈/心不全を起こしやすくなる/夏バテしやすくなる/食欲不振】
【多く含まれる食品:リンゴ/スイカ/干し柿/インゲン/納豆/枝豆 など】
ナトリウム(Na)
細胞外液の浸透圧を調節して、細胞外液量を保つなどの役割を持っています。 通常、健康な人では欠乏することはありません。
【主な働き:カリウムとどに細胞の浸透圧を調整/神経に刺激を伝達】
不足すると、吐き気、疲労感、頭痛、全身倦怠、筋けいれん、意識障害、昏睡などがあります。
多く見られる低Na血症の原因は、大量飲水(1リットル/時以上)、下痢、嘔吐、過度の運動、高齢、心不全、肝不全、腎不全、薬物使用などです。
【主な欠乏症:脱水症状/血圧低下/腎臓が弱くなる/日射病】
【多く含まれる食品:食塩/醤油/味噌/コンソメスープの素 など】

マグネシウム(Mg)
300種類以上の酵素を活性化する働きがあり、筋肉の収縮や神経情報の伝達、体温・血圧の調整にも役立っています。
【主な働き:精神の安定/体温や血圧の調整/心臓の筋肉の動きを良くする】
不足すると、骨の形成に影響が出るほか、不整脈や虚血性心疾患、高血圧、筋肉の痙攣を引き起こします。 また神経過敏や抑うつ感などが生じることもあります。
【主な欠乏症:不整脈/精神不安定/心臓発作を起こしやすくなる】
【多く含まれる食品:カシューナッツ/アーモンド/大豆/落花生/納豆/海藻 など】
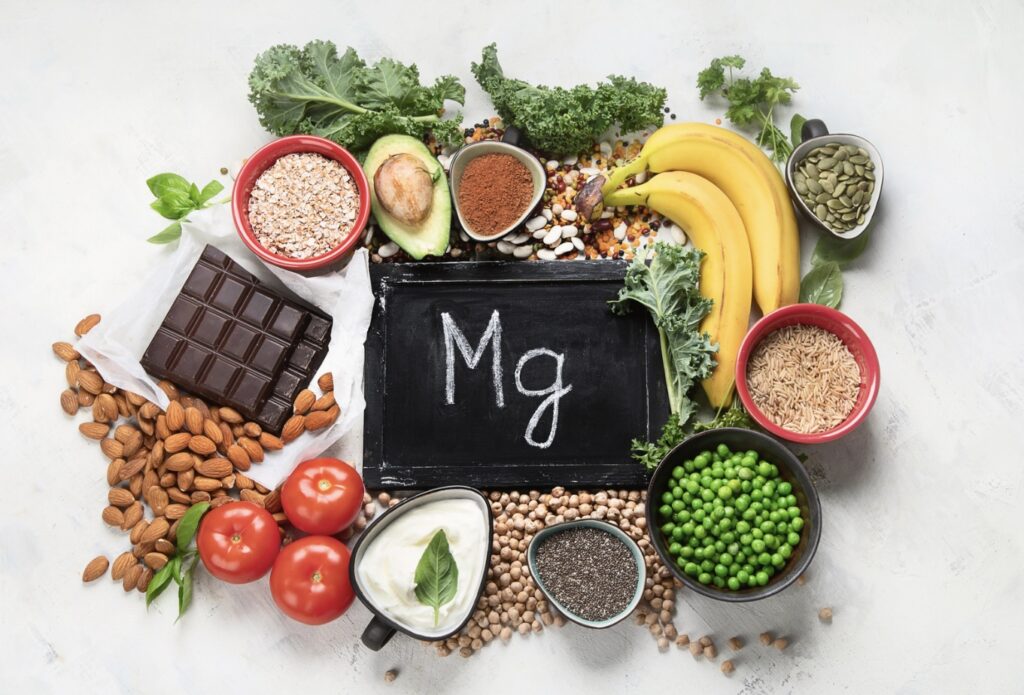
微量無機質
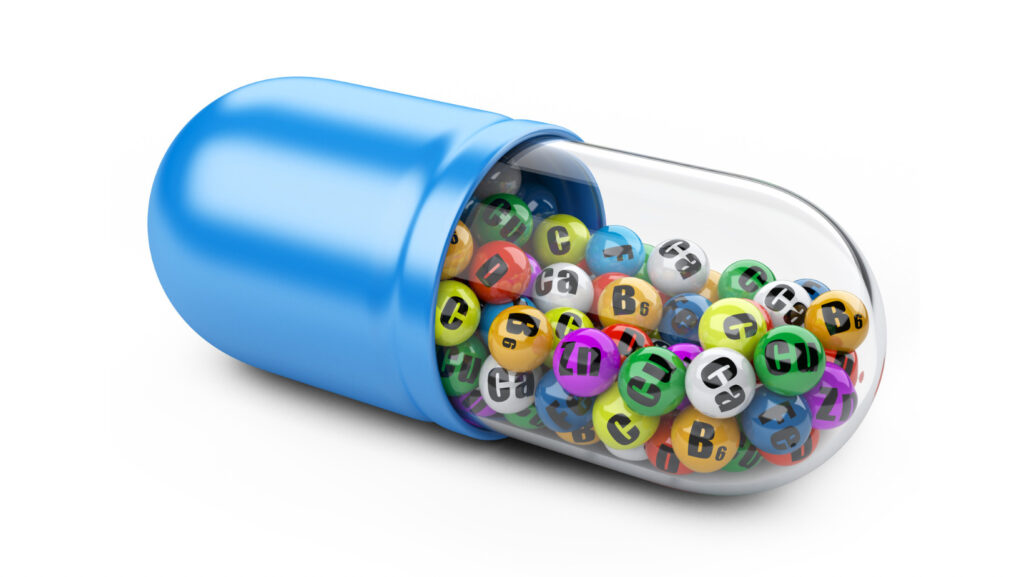
鉄(Fe)
主な働きは全身に酸素を運搬することです。
鉄の適量摂取は運動能力や学習能力の向上が期待できます。
【主な働き:成長促進/疲労を防ぐ/ヘモグロビンの成分となる】
不足すると、脳へ酸素がいきわたりにくくなり、思考力、学習能力、記憶力の低下につながります。
【主な欠乏症:貧血/集中力の低下/思考力の低下/肩・首筋が凝る】
【多く含まれる食品:レバー/魚介類/ホウレンソウ/小松菜 など】

亜鉛(Zn)
人間の健康維持に必須であるミネラルの一つで、味覚を正常に保ったり皮膚などの健康維持に関わったりする効果があります。
【主な働き:味覚・嗅覚を正常に保つ/ビタミンCとともにコラーゲンを合成/性能力の維持】
不足すると、味覚障害や皮膚炎などの症状が起きます。
【主な欠乏症:味覚異常/情緒不安定/脱毛症】
【多く含まれる食品:カキ/レバー/ホタテ/肉類/卵 など】

マンガン(Mn)
血液の生成血液やビタミンE複合体の一種を、体内で生成するときに関係します。
消化補助体内の消化作用をサポートし、骨や靭帯、神経を強くします。 下垂体を活性化脳にある下垂体の機能を高める働きがあります
【主な働き:骨の形成/疲労回復】
不足すると、全身倦怠感、易疲労感と意欲の乏しさを主徴とし、また、ねむけ、記銘・記憶障害、時には頑固な不眠、さらには食思不振などがあげられます。
【主な欠乏症:平衝感覚の低下/疲労しやすくなる】
【多く含まれる食品:玄米/大豆/アーモンド など】
ヨウ素
全身の基礎代謝を向上させて呼吸を早め、酸素の消費量を高めたり、心臓の働きを強くして脈拍数や心拍出量を増やします。
【主な働き:成長促進/甲状腺ホルモンの成分】
不足すると、甲状腺機能低下症によって、皮膚の浮腫、声がれ、精神機能障害、皮膚が乾燥しうろこ状になる、毛髪が硬く薄くなる、寒さに耐えられない、体重増加といった症状が生じることがあります。
妊婦がヨウ素欠乏症になると、流産と死産のリスクが増大します。胎児の成長が遅くなることもあり、脳の発達に異常が現れることもあります。
【主な欠乏症:甲状腺腫/疲労しやすくなり、機敏さがなくなる】
【多くの含まれる食品:昆布/ワカメ/海苔 など】

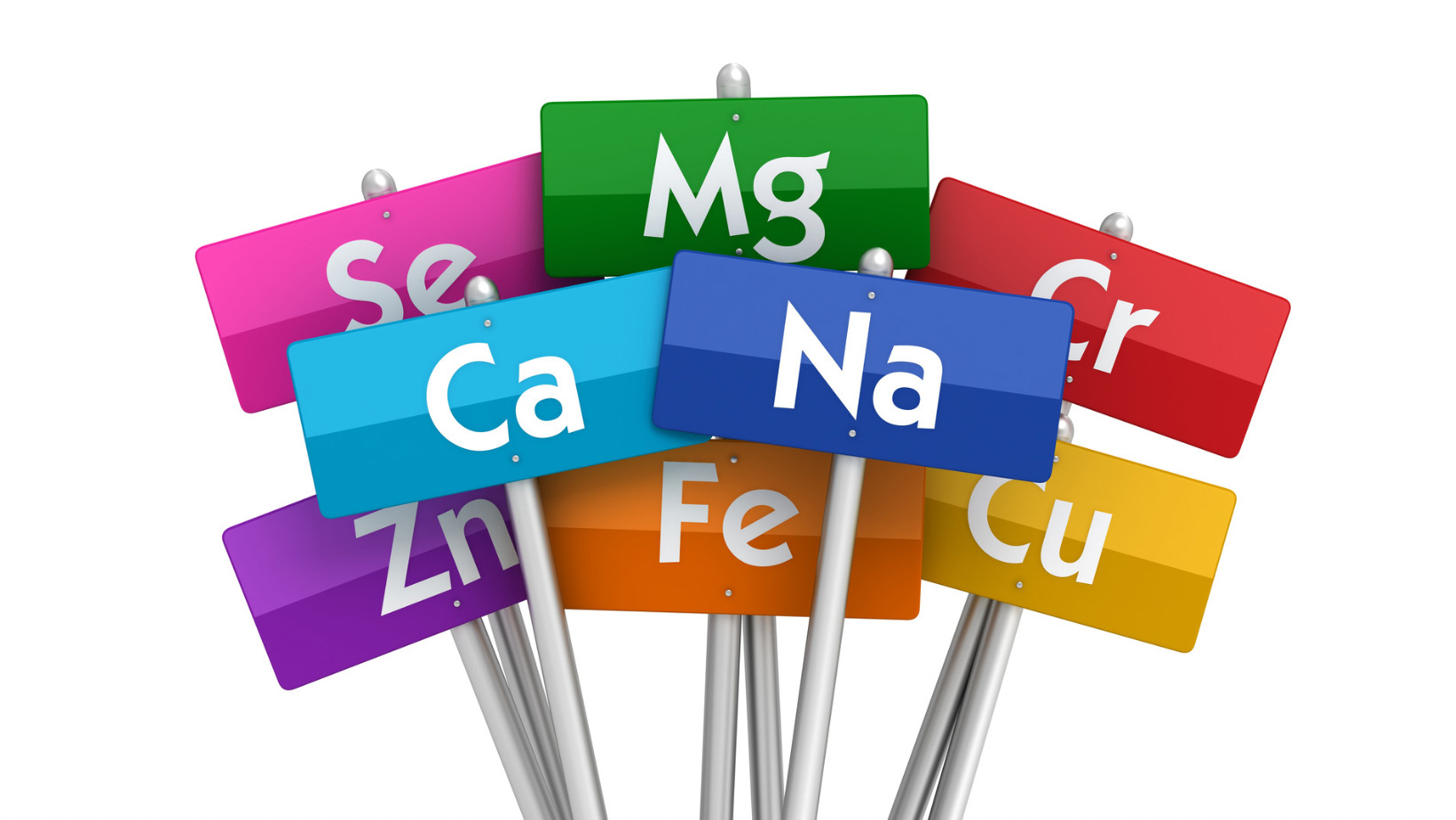


コメント