今回は、郷土料理や、その土地(産地)の食べ物・豆知識を、紹介していきます☆
郷土料理と地産地消☆環境に優しく

日本には地域ごとの文化や歴史、人々の生活の知恵に基づいた食=郷土料理というものがあるピヨ!
地域の文化を映す郷土料理
日本は気候風土が多彩で、その土地ならではの特産物や気候を生かした郷土料理が生まれ、継承されてきています。
郷土料理は、その成り立ちや、食材、調理方法によって4つに分けられます◎
①その土地特有の生活習慣や自然、気候などの条件のもとで、人々の知恵や工夫から生まれ、受け継がれてきた料理。
②地域の特産品を、その土地特有の調理方法で作った料理
③料理方法は地域を問わない一般的なものだか、その土地特有の食材を使った料理。
④食材は地域を問わない一般的なものだが、その土地特有のは料理方法で作った料理。
日本の主な郷土料理
日本の有名な郷土料理を一部、紹介します◎

- 北海道=石狩鍋・松前漬け
- 秋田=しょっつる・きりたんぽ
- 岩手=わんこそば
- 山形=納豆汁
- 宮城=笹かまぼこ
- 新潟=わっぱめし・のっぺい煮
- 富山=いかの墨作り・ますずし
- 山梨=ほうとう・煮貝
- 長野=五平餅・鯉こく
- 徳島=鮎ずし
- 高知=鰹めし・皿鉢料理
- 福岡=筑前煮
- 長崎=卓袱料理
- 鹿児島=さつま汁

地産地消と土産土法の考え方
地元で生産(収穫)されたものを食べることが、カラダに良いという考え方を身土不二といいます。
▶︎身(カラダ)と土(土地からの恵み)は二つではなく(不二)、同じものであるという意味で、地元の作物を食べることがカラダにとって良いという考え方。

地元の自然に適応した作物を食べることが、そこで生活する人のカラダにとってもっとも自然で健康的だという意味だピヨ!
地産地消
その土地で生産(収穫)された食物を、その土地の食べ方で食べることや、その土地で消費することが望ましいという考え方で、
『域内消費』とも呼ばれます◎
全ての食材を地域内で賄おうという地域自給という言葉もあります。
土産土法
その土地で生産(収穫)された食物は、その土地特有の調理方法で料理・保存したり、食べることが望ましいという考え方です。
収穫してから時間を置かずに新鮮なうちに食べることができます◎

生産された土地ならではの調理方法や保存方法は、食材の良さを活かして、もっともおいしく食べることができるピヨ!
地産地消・土産土法のメリット☆
- 生産者と消費者の結び付き
- 食生活を健康的に
- 食の安心・安全
- 食料自給率アップ
- 地域の活性化
- 食文化への理解
- 環境にやさしい
スローフード運動
イタリアで1986年に始まって以来、日本を含め世界中に広がっている、食文化を守ろう・大切にしようという活動です。
〜スローフード運動の三つの活動〜
- 消えゆく可能性のある郷土料理や質の高い食品を守る
- 質の高い食材を生産・供給してくれる小規模生産者を守る
- 子どもたちを含む、多くの消費者に本来の味の教育を進める

スローフードとは、『安価で効率が良く、早く出てきて、どこで食べても同じ味』というファストフードに対する言葉だピヨ!
フードマイレージ運動
スーパーマーケットなどで売られている生野菜や鮮魚には、外国から輸入されているものも多くあります。
農産物などの食料が、生産地から消費される土地まで輸送される距離が長ければ長いほど、輸送に使われる燃料などのエネルギーが大きくなり、二酸化炭素(CO2)の排出量も増え、環境にかかる負荷が大きくなります。
その事から、住んでいる地域の近くの食材を食べるようにすれば、輸送に伴うエネルギーを減らすことができ、環境への負担を少なくすることができるという考えで、
食材が輸入され、消費者の口に入るまでの距離を数字で表し、できるだけ近くで生産されたものを消費しようという取り組みをフードマイレージ運動といいます◎
フードマイレージの計算
輸入相手国別の食料輸入量(t)✖️輸出国から日本までの輸送距離(km)🟰フードマイレージ(tkm/トンキロメートル)


郷土料理は、その土地の食材、美味しい食べ方だけでなく、最後には環境(地球)にも優しい流れになっているピヨね!
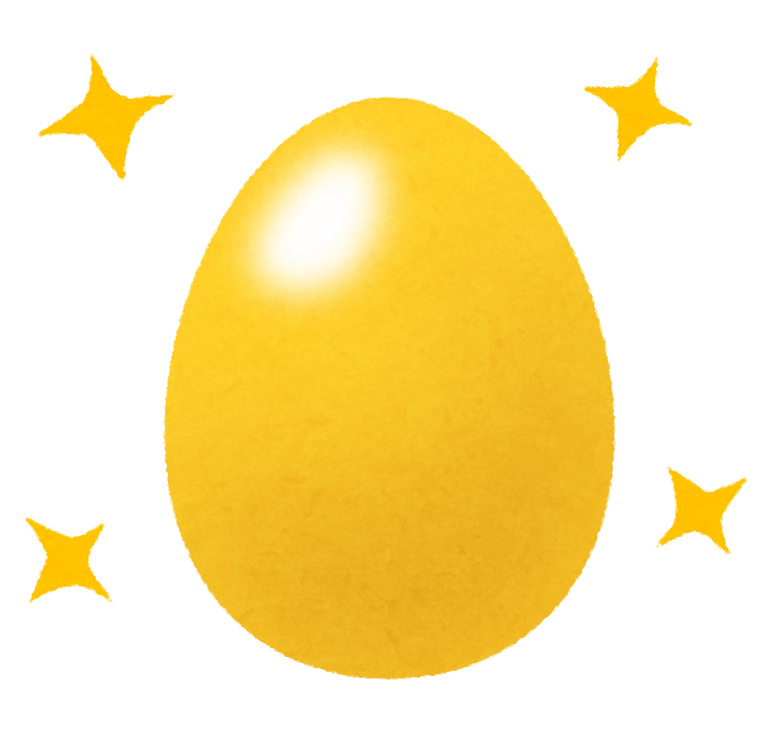
そうなんです!
食材(食べ物)や環境にとっても優しい活動なので、自然や地球を大切にできる事が、嬉しいポイントでもあります♪
この様に、郷土料理/地産地消・土産土法/スローフード運動・フードマイレージ運動は、その土地の食材を美味しく食べるだけではなく、環境にもやさしく配慮した、取り組みです◎
以上、今回は、郷土料理と地産地消☆環境に優しくについての紹介でした☆


コメント